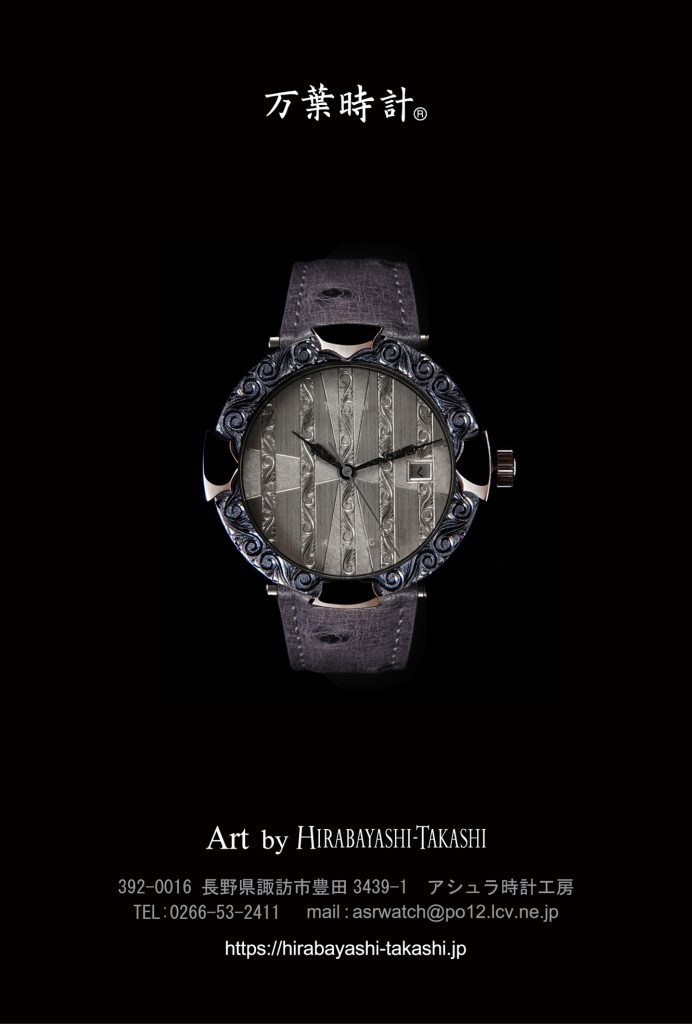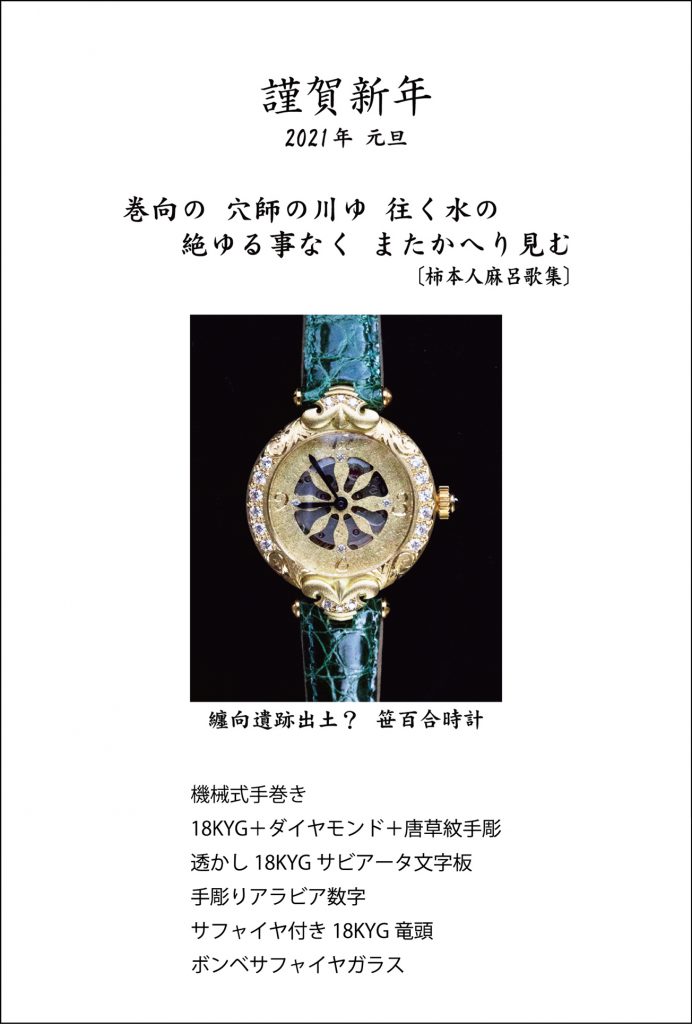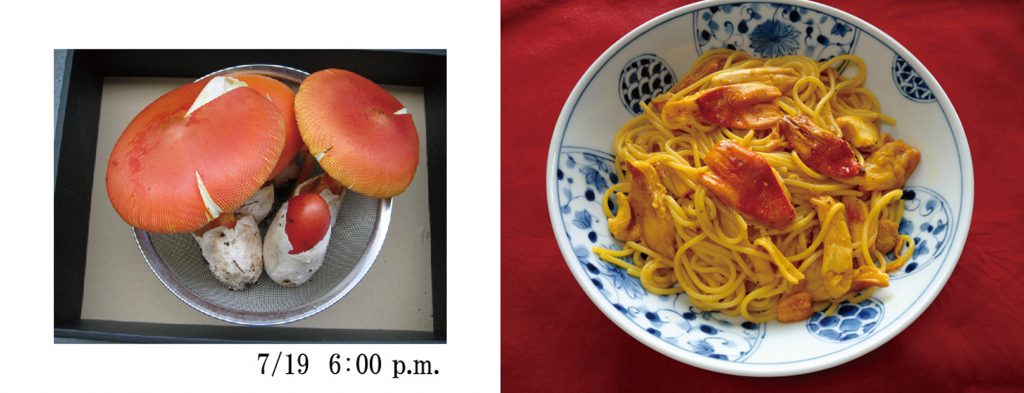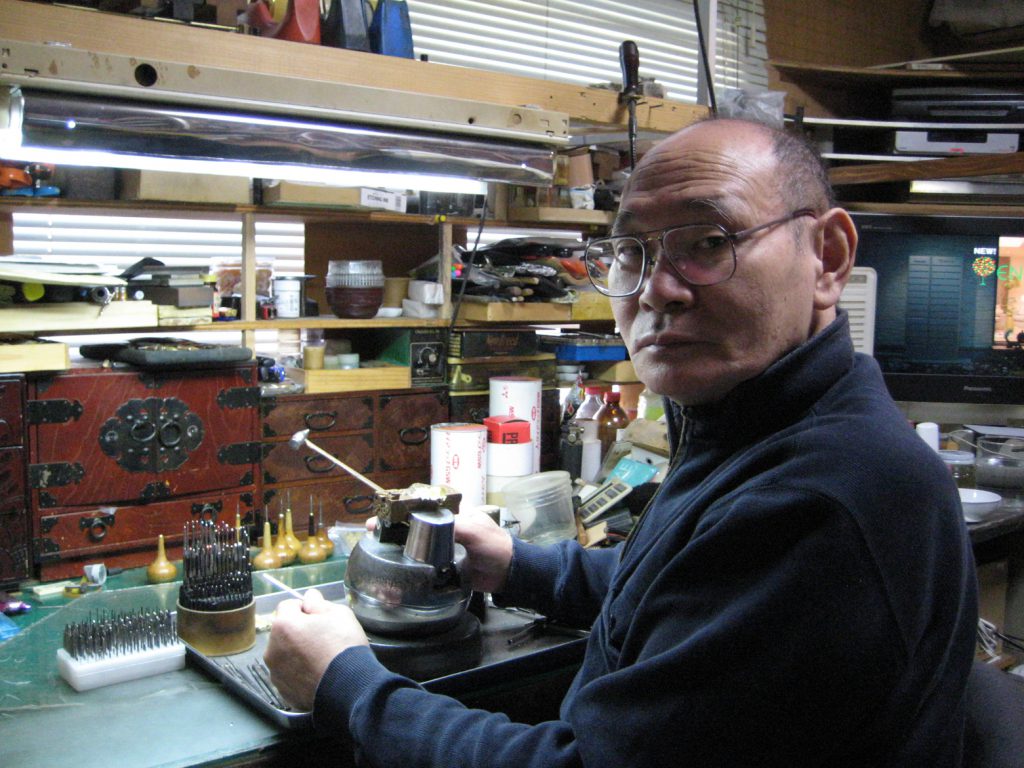あしひきの 山川の瀬の 響るなへに 弓月が岳に 雲立ち渡る (万葉集 7-1088)
柿本人麻呂歌集出の万葉集1088の詩には雄大でかつ澄んだ瀬音と雲や蒸気の動きまでも感じさせる文学史上の白眉と感じざるを得ません。偉大な詩です。1300年経てもなお現代人に感銘を起こさせる。時の試練を超えて現代に生き残っていることの驚異。賀茂真淵や斉藤茂吉、梅原猛氏に動機を与え続ける事実に言葉の持つ力と大切さを痛感いたします。日本の宝です。
あまりに雄大な印象ゆえに2000m超えの山並みと感じてしまうのですが、海抜は低く三輪山467m、巻向山で567mです。「たたなずく青垣 山隠れる」とはこのような地域を指すのかと納得させられます。アルプスのような険しい岩肌ではいけないのです。
やまとことばの特性にも気を配った韻律、音の運びの心地よさ。
たった三十一文字で31音なのに読み手に清らかな川の音(眼の前)から弓月が岳の山頂(遠景)に視点を移動させ雲の上昇気流を眺めている様。
他の和歌を見れば古代にも巻向山は存在していて、言葉の創造者である人麻呂は巻向山から昇る弓の形をした月をみて「弓月が岳」と例えたのではないでしょうか。試に、
あしひきの 山川の瀬の 響るなへに 巻向山に 雲立ち渡る
と詠んでみますと「弓月が岳」の字句が極めて秀逸であることが判ります。
「響るなへに」と「響」を当てていることで瀬音も引き立てます。
弓月が岳は由槻や斎槻とも表記されるので古代には槻の樹(けやき)が林立していたものと想起されます。日本固有種であり大木ゆえ古民家では大黒柱に使われてきました。
そこで詩歌の詠まれた故地、弓月が岳の自然環境と産土神に触れてみたいと思い立ち、桜井市のボランティアガイド長をされた福本氏に候補地をガイドして頂きました。
2017年3月に「夏至の大平」、6月に「巻向山」に登拝しました。
登拝前には穴師坐兵主神社と十二柱神社に献饌、参拝を済ませました。
記憶に残る体験でした。巻向山へは途上、磐座を経由しました。
磐座祭祀ですと、出雲系の神々を祀っていますし、十二柱神社の住所は桜井市出雲なのが興味深い。
人麻呂の素晴らしい詩に感応していますと美しい言葉が響き、ものを観察する眼識までも磨かれ感性のヴァ―ジョンアップが図られるように思えてきます。この後も人麻呂作歌についての感慨を投稿してみたいと思います。
原文 足引之 山河之瀬之 響苗尓 弓月高 雲立渡
令和和歌所へ寄稿 https://wakadokoro.com/category/contribution/